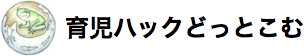井戸の中しか知らない自慢ガエル。
皆と仲良く遊びたいのに、周りにいる蛙や おたまじゃくしをけなしたり、馬鹿にしたり、自分の自慢ばかり。
いつものように自慢ばかりしていたら、一人ぼっちになっていた。
そんな時に、渡り鳥と出会い、旅に出る。そこで、自慢ガエルが体験したことは・・・




上手な自己主張が下手な子や、やる前から出来ない、少しやって出来ないとすぐにやめてしまう子供達にお勧めの絵本です。
この絵本も、「みんなみんな ありがとう」の絵本と同様に、英語でも読めるようになっています。
いどのなかの じまんガエル
Idono nakano jiman gaeru / The frog in the well knows nothing of the great ocean
作・絵 川島 千賀子
ソフトカバー NZ$15
ISBN 978-0-473-29361-1
「いどのなかの じまんガエル」の絵本制作のきっかけ
私がグループで遊んでいる子供たちを見て、子供が上手な自己主張ができるようにならないかと思ったのが制作のきっかけでした。当時、ゆっくり成長するタイプの息子は、他の子供たちに、出来なくてけなされることが多く、またそういった時に、黙って我慢していました。
アドラー心理学の自己主張を分類分けすると、
1、相手を傷つけてまで、自分の要求や主張をする攻撃的自己主張。
2、自分の気持ちを言わず、黙って我慢する非自己主張。
3、相手を傷つけずに自分の意見を言う主張的自己主張。
4、自分の意見も言わず、相手を傷つける復讐的自己主張 の4つに分類します。
絵本を通して、非自己主張をする息子に、主張的な自己主張を学んで欲しいと思い、自慢ガエルに反論する会話を入れました。渡り鳥は、体験から学ぶ大切さを伝える為に登場させ、しだいに勇気づけの絵本へと変化していき、この絵本も長い間、試行錯誤をしました。そうして、長い年月とともに息子は、前よりも上手に主張的自己主張が出来るようになりました。しかし今度は、時々、自慢ガエルになるという問題が発生するようになり、今では違う方向からこの絵本を利用するようになりました。
また、絵本のじまんガエルは、特別な存在ではなく、私自身が気を付けていないと子供にやってしまいがちな対応です。例えば、子供がお絵描きを楽しんでいるとき、鉛筆の持ち方が違うと持ち方を指導してしまう場合などです。こういった時、楽しかったお絵描きがつまらないものに変化します。子供が今、楽しんでいることを一緒に楽しむこと、子供を尊敬する心を忘れないために、この絵本も自分自身の為に作ったのかもしれません。
「みんなみんな ありがとう」と「いどのなかの じまんガエル」の2冊の絵本を通して、私が子供たちに伝えたかったことは、この世のすべてがかけがいのない素晴らしいもの。さらに個々が何かに挑戦したり、たとえ上手に出来なくても努力や失敗の経験がその人の財産となり、今の環境を作っているということ。今を楽しむには、自分自身や相手の気持ちを想像する力、今よりもより良くするには、良い状態を強くイメージすること。何をするにもイメージ力が重要だと言うメッセージもこめました。私は、アドラー心理学の絵本として、また、たくさんの思いをこめて制作しましたが、言葉遊びや荘子、蛙の歌の絵本としても楽しんで頂けたら幸いです。